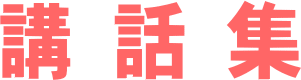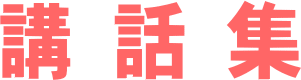|
N日報という新聞紙の本年2月の記事と記憶している。「大腸がんは切っても切らなくても生存期間に大差がなかった」という内容だった。
詳しく言うために以下、引用する。『グループでおととしまでの7年間に治療を受けたステージ4の大腸がんの患者160人について、大腸にあるがんを切除した人と切除しなかった人で半数が生存していた期間を比べたところ、どちらも2年2か月ほどで差がなかったほか、切除した人の方が抗がん剤を受けたときに重い副作用が出る頻度が高かったことが分かった』というものだった。
以前から筆者は「内科は東洋医学で行うべきで外科では内科の病気の治療は適さない」と主張して来た。
 切除がどれほど有効でないかのデータが、一部であるが今回示されたこととなり、筆者の主張の傍証にはなると考えて良かろう。 切除がどれほど有効でないかのデータが、一部であるが今回示されたこととなり、筆者の主張の傍証にはなると考えて良かろう。
だがそれでも、それを凌ぐ治療として、手術せずに抗がん剤のみを使う治療が標準になる、とこの記事では述べていた。
しかし抗がん剤が有効とされる原理は、がん細胞を含めすべての臓器の力を抗がん剤が低下させるからなのである。つまり抗がん剤が効くとは健全な臓器の能力が低下させられるからなのである。
抗がん剤が効くという事はがん細胞へ作用する前に、健常な臓器が弱る事を意味する。効かないという事はがん以外の他の臓器が健常な状態のままでいるという事になる。
それをして抗がん剤が効いたという解釈してしまう。なんで抗がん剤治療で患者の体力のロスをさせている現実を判ろうとしないのか不思議だ。体力のロスよりガンを制する方が重要という事になるが、重要というその根拠はない。
西洋医学と東洋医学の視点の違いと言えばそうだが、一部を治すために全体を弱らせる…そのことを治療と称する事は既に治療と言えまい。
 一体、西洋医学はガンを初めとして病気をどう考えているのか…「病んでいる人がおられたらつい手を出して治そうとする…それが医師の業病だ」と仰るドクターは立派ではある。だが全ての病気は永遠に治る訳ではない、永遠には治せない。 一体、西洋医学はガンを初めとして病気をどう考えているのか…「病んでいる人がおられたらつい手を出して治そうとする…それが医師の業病だ」と仰るドクターは立派ではある。だが全ての病気は永遠に治る訳ではない、永遠には治せない。
人は必ず死ぬ、遅かれ早かれ死ぬのだ。どんな難病が治ったとしても、いずれ死ぬ。それなのに、難病が治った事を喜ぶ。どんな病気が治ろうと、人は永遠には生きては行けない。
それが全ての命の現実なのだから、治すことにどれほど意味があるのだろう。意味はあるとして、それほど大きなものなのだろうか。痛くなく生きられるならそれでよしとし、それを治療とすべきではないだろうか。
痛くなく生きる事をもっと研究すべきではないか。その人らしく尊厳を持って死に臨むことを治療の第一にすべきではないのか。
命はドクターがどんなに頑張っても届かぬ存在である。いや人の手の届く存在にしてはならないのが命なるもので、つまる所、命は神の握るものでしかない。
 神の意に反して長命に生きさせられる…、それは自分らしさへの冒涜ではないか…。長生きしても自分らしくないのなら、それは苦痛でしかないからだ。 神の意に反して長命に生きさせられる…、それは自分らしさへの冒涜ではないか…。長生きしても自分らしくないのなら、それは苦痛でしかないからだ。
現代の西洋医学はまさにそれである。病む人の家族もドクターも命続く事に目標を置くが、それは手品でしか行えないことに気づかない。
件の抗ガン治療は体全体の体力をそぐことに尽きる。母体が弱るから寄生しているガンが元気を奪われる…だから痛めなくなる。だが、母体を傷めることになる…傷めた結果でガンは小さくなる、ならざる得を得ない。だがガンが小さくなるだけで消滅する訳でない。
だからガンの場合は治癒ではなく『寛解』と称する。ガンはどこにでも巣を組みますよ、でも今はがん細胞が巣を組んでいません…それをして寛解と呼び、寛解をして治ったことにしているだけだ。
それで限界だと予感するなら、治療そのものを疑う事はありじゃないか。人は死ぬる存在で、だから治せない病気があって、楽に死ぬように導く…のがその場合の治療だと思う
|